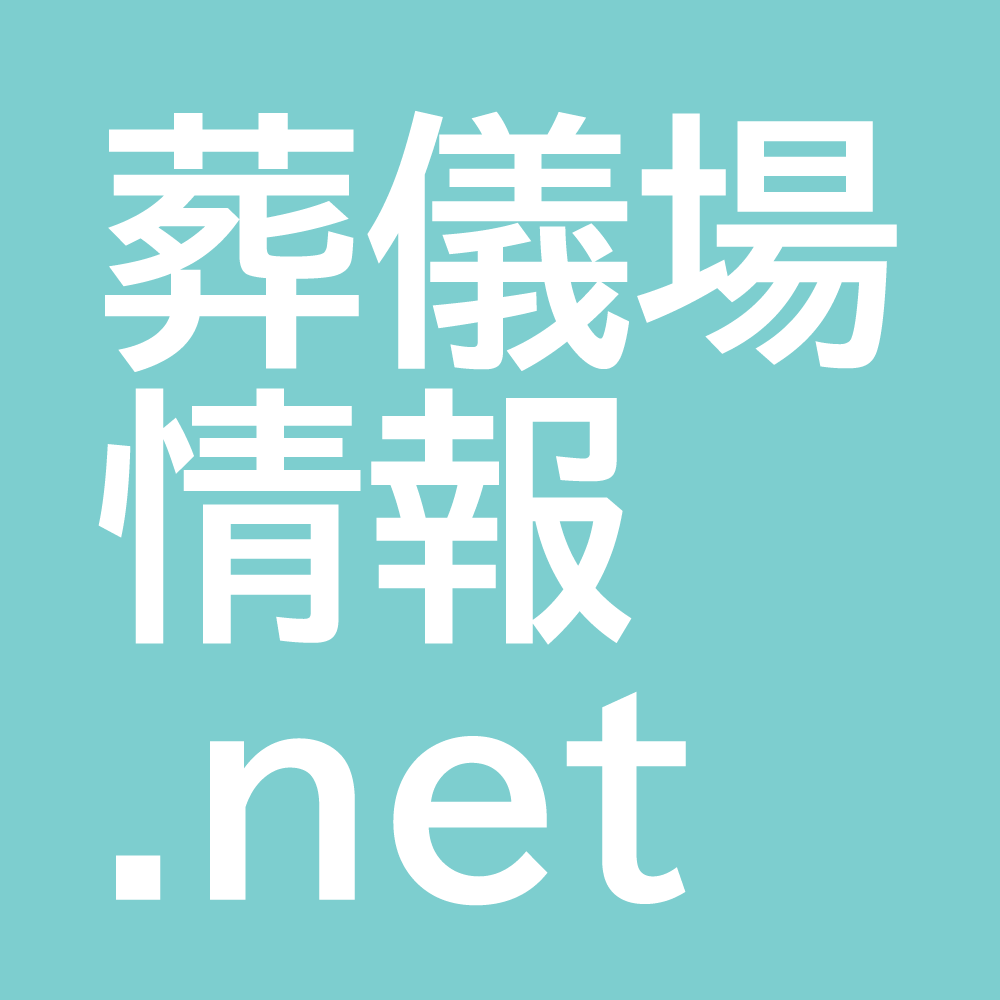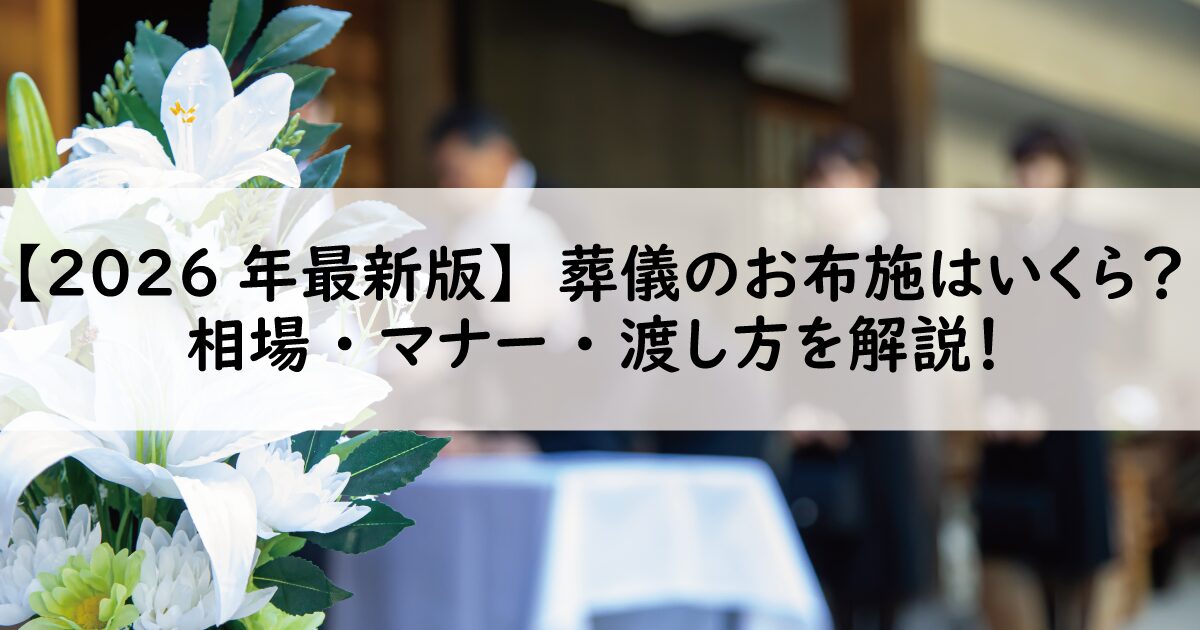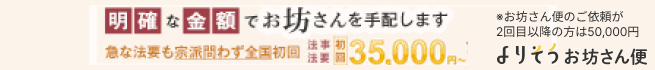【2026年最新版】葬儀のお布施はいくら?相場・マナー・渡し方を徹底解説
【PR】
葬儀でお布施はいくら包めばいいのか分からない方へ
葬儀を行う際、多くの方が悩むのが「お布施」の金額です。そもそもお布施とは、僧侶に読経や戒名、葬儀全般の対応をお願いした際に渡す謝礼のこと。金額が明確に決まっているわけではなく、地域や宗派、僧侶の経験によって差があります。そのため、「どれくらい包めば失礼にならないのか」「多すぎても少なすぎてもいけないのでは」と心配になる方が多いのです。
初めての葬儀であれば、金額の目安やマナーを知らないことは自然なことです。
無理に高額を包む必要はありませんが、最低限の相場を知っておくことで、心を込めた供養ができます。葬儀のお布施の相場や渡し方、封筒の書き方など、初心者でも安心して準備できるポイントをわかりやすく解説します。
相場が分からず失礼になるのが心配
お布施は、単なるお金のやり取りではなく、「感謝の気持ち」を形にするものです。そのため、金額が少なすぎると僧侶に失礼にあたるのでは、と心配する方もいます。一方で、相場以上に包むことが必ずしも良いとは限りません。大切なのは、僧侶の労力や葬儀の規模に見合った金額を適切に渡すことです。
お布施の金額は、通夜や告別式、戒名料、法要の種類によっても異なります。例えば、通夜と告別式の両方で読経をお願いする場合は数万円〜十数万円程度、初七日や四十九日などの法要では別途包む場合があります。また、地域や宗派によっても目安が変わるため、事前に確認しておくと安心です。
最近では、葬儀費用やお布施の相談に乗ってくれる専門サービスも増えています。例えば、「葬儀のこれから」では、全国の僧侶派遣や費用見積もりに対応しており、初心者でも安心して葬儀の準備を進められます。相場やマナーに不安がある方は、こうしたサービスを利用するのも一つの方法です。
葬儀は大切な方を見送る儀式です。お布施の金額や渡し方で迷う必要はありません。大切なのは、心を込めて感謝を伝えることです。誰でも安心してお布施を準備できるように、金額の目安や渡し方、封筒の書き方を紹介しますのでご参考ください。知識を持っておくことによって、葬儀の当日も落ち着いて対応できるでしょう。
お布施とは?意味と支払いの目的
僧侶への謝礼としての役割
お布施とは、葬儀や法事で僧侶に渡す謝礼のことです。通夜や告別式での読経、戒名授与、法要の執行などに対する感謝の気持ちを金額として表すものです。お布施の金額は決まっていませんが、僧侶の労力や葬儀の規模に応じて包むのが一般的です。
寄付や“供養を買う”ものではない
お布施は「お金で供養を買う」ためのものではありません。葬儀の成功や故人の成仏を保証するものではなく、あくまで僧侶に対する感謝と敬意を示す手段です。この点を理解しておくことで、過剰に金額を心配する必要はなくなります。
感謝の気持ちを形にするもの
お布施は、言葉では伝えきれない感謝の気持ちを形にする手段です。封筒の書き方や渡し方にも心配りをすることで、僧侶への敬意を伝えることができます。金額よりも、心を込めて準備することが大切です。
葬儀のお布施の相場はいくら?
一般的な相場の目安
葬儀での通夜・告別式・戒名料を含めたお布施の総額は、一般的に 5万〜20万円程度 が目安です。金額は僧侶の経験や地域、葬儀の規模によって変わります。都市部ではやや高め、地方では平均的に低めになる傾向があります。また、宗派によって戒名料の相場が異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
法要・法事のお布施相場
初七日や四十九日、一周忌などの法要でのお布施は、通夜・告別式とは別に包む場合があります。目安として 3万〜5万円程度 が一般的です。ただし、葬儀と同日に行う場合は減額されることもあります。また、読経の長さや会場(自宅・寺院)によっても金額は変動するため、柔軟に対応することが大切です。
お布施の金額早見表
| 内容 | 相場の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 通夜・告別式・戒名料 | 5〜20万円 | 僧侶の読経・戒名料含む |
| 初七日法要 | 3〜5万円 | 葬儀と同日なら減額のことも |
| 四十九日法要 | 3〜5万円 | 自宅・寺院で変動 |
お布施の渡し方とマナー
封筒の書き方
お布施を包む封筒には、表書きとして 「御布施」 や 「御礼」 を使います。違いとしては、「御布施」は葬儀や法要全般に、「御礼」は僧侶への感謝の気持ちを表す場面で使われます。封筒は無地の白封筒や双銀の水引を用い、裏面には住所と名前を丁寧に記入します。
渡すタイミングと場所
お布施は、葬儀や法要の終了後に僧侶へ直接渡すのが基本です。式場によっては受付経由で渡す場合もあります。渡す際は 袱紗(ふくさ) に包み、両手で丁寧に差し出すことで、感謝の気持ちを表せます。
お車代・御膳料の相場
遠方から来てくれた僧侶には、移動費として お車代5,000〜10,000円 を包むことが一般的です。また、葬儀後の食事を辞退する場合には 御膳料5,000円前後 をお渡しするとマナーに沿います。これらもお布施同様、心を込めて用意することが大切です。
「よりそうお坊さん便」を使うとどう費用が変わる?
| 観点 | 一般的なお布施相場 | よりそうお坊さん便 | 変わるポイント |
|---|---|---|---|
| 費用の形態 | 目安が不明瞭で寺院ごとに差がある | 定額料金で明確 | 追加費用が発生しにくく、総額を予測しやすい |
| 料金の安心感 | 当日まで総額が読めない場合も | 戒名・通夜・葬儀・法事まで内容込み | 固定料金で心配を軽減 |
| 家族葬との相性 | 式場や僧侶への説明が必要な場合も | 依頼内容を一括で共有できる | 小規模な式でもスムーズに手配可能 |
| 急ぎの対応 | 寺院の都合に左右される | 急な日程にも対応 | 予定を組みやすい |
「よりそうお坊さん便」なら
法事・法要の読経は【初回35,000円】 ※2回目以降は45,000円
葬儀読経は【35,000円~】
戒名授与は【20,000円~】
お布施でよくある疑問Q&A
Q1:お布施の金額を相談してもいい?
初めて葬儀を行う方にとって、お布施の金額は不安の種になりやすいものです。「多すぎても少なすぎても失礼ではないか」と迷う方も少なくありません。実は、僧侶に直接金額を相談しても問題ありません。特に、地域や宗派によって目安が異なる場合は、事前に確認しておくと安心です。相談の際には、丁寧に「葬儀の規模や費用に合わせて教えていただけますか」と聞くと、柔らかい印象になります。
Q2:複数の僧侶が来た場合はどうする?
葬儀によっては、複数の僧侶が読経や戒名授与を担当することがあります。この場合は、それぞれの僧侶にお布施を包む必要があります。金額は基本的に均等に分けるのが一般的です。例えば、総額10万円のお布施を二人の僧侶に渡す場合は、各5万円ずつ包む形です。どちらか一方だけにまとめて渡すのは避け、均等に渡すことで失礼がなく、感謝の気持ちも伝わります。
Q3:お布施を現金書留で送ってもいい?
遠方のため葬儀に参列できない場合や、当日直接渡せない場合には、現金書留で送ることも可能です。この場合、封筒には「御布施」と明記し、住所・名前も記入します。封筒を二重にするなどして安全に送ることが大切です。また、送付する際には、僧侶や寺院に事前に連絡しておくと丁寧です。「現金で失礼にならないか」と心配する必要はなく、心を込めて準備していることが伝われば問題ありません。
Q4:その他のよくある疑問
-
お布施は領収書をもらえるのか?
寺院によっては希望すれば領収書を発行してくれます。特に会社や団体で葬儀を行う場合は、事前に確認しておくと安心です。 -
金額は現金でしか渡せないのか?
基本は現金ですが、現金書留以外に電子決済や銀行振込に対応している寺院も増えています。事前に相談するとスムーズです。 -
親族以外が渡す場合はどうする?
親族に代わって渡す場合も、袱紗に包んで両手で渡すなど、マナーは変わりません。
お布施は「金額の多さ」よりも「心を込めて渡すこと」が大切です。疑問や不安がある場合は、遠慮せず僧侶や葬儀社に相談することで、安心して準備できます。初心者でも、相場やマナーを押さえておけば、落ち着いて葬儀に臨むことができるでしょう。
トラブルを避けるためのポイント
事前に金額を確認・相談する
お布施でのトラブルを避けるためには、まず 金額を事前に確認すること が重要です。葬儀の規模や読経の時間、僧侶の経験によって金額は変わるため、あらかじめ葬儀社や寺院に相談しておくと安心です。「これくらいが一般的でしょうか」と聞くだけでも失礼にはなりません。
戒名料が別か含まれているか確認
お布施の中に 戒名料が含まれているかどうか もチェックポイントです。戒名料が別料金の場合は、別途用意する必要があります。事前に確認しておけば、当日慌てることなく適切な金額を包むことができます。
領収書をもらう場合の注意点
会社や団体で葬儀を行う場合、領収書が必要なことがあります。領収書を希望する場合は、事前に寺院に確認しておきましょう。希望しないと発行してもらえない場合もありますので、必ず事前のやり取りを行うことがトラブル回避につながります。
葬儀サービス紹介
葬儀のお布施や費用、マナーに不安を感じる方は少なくありません。そんなときに頼れるのが 「安心葬儀」 です。
「安心葬儀」の特徴
- 全国20,000以上の葬儀社・斎場と提携し、条件に合う葬儀社を紹介。
- 一括見積もりで最大3社のプランを比較でき、費用やサービス内容の透明性を支援。
- 24時間365日、電話やメールで無料相談が可能で、急な訃報時にも対応。
- 葬儀を実施する葬儀社と相談者との間に入り、「しつこい営業なし」「キャンセル代行」など利用者の負担と不安を軽減。
葬儀の準備は、金額やマナーの不安だけでなく、式の手配や日程調整などやることが多く大変です。「安心葬儀」を利用すれば、費用やお布施の目安も含めてプロに相談でき、トラブルや迷いを最小限に抑えることができます。
初心者の方も、これまで葬儀の経験がない方も、安心して故人を見送るためのサポートが整っています。お布施の相場や渡し方に迷ったときも、スタッフが丁寧に案内してくれるので安心です。
お布施や葬儀の準備で悩む前に、まずは見積もりや相談をしてみましょう。
「葬儀のこれから」
-
料金が明確:お布施や式費用、オプション料金まで事前に見積もり可能
-
全国対応:地方や遠方でも手配可能、移動費やお車代の目安も提示
-
初心者でも安心:僧侶へのお布施の目安や渡し方など、わかりやすく案内
-
口コミ評価が高い:実際に利用した方の声を確認でき、信頼できる
葬儀の準備は、金額やマナーの不安だけでなく、式の手配や日程調整などやることが多く大変です。「葬儀のこれから」を利用すれば、費用やお布施の目安も含めてプロに相談でき、トラブルや迷いを最小限に抑えることができます。
初心者の方も、これまで葬儀の経験がない方も、安心して故人を見送るためのサポートが整っています。お布施の相場や渡し方に迷ったときも、スタッフが丁寧に案内してくれるので安心です。
「お布施の金額がわからない」「信頼できる葬儀社を選びたい」という方は、まずは「これから」の無料相談 を利用してみてください。
専門スタッフがご家族の状況に合わせて、無理のない最適なプランを提案してくれます。
\24時間受付の相談窓口と便利な「喪主のためのガイドブック」無料進呈/
お布施の相場を知って、心を込めた葬儀を
お布施は、僧侶への謝礼というだけでなく、故人への感謝の気持ちを形にする大切なものです。金額の相場や封筒の書き方、渡し方のマナーを事前に知っておくことで、当日慌てずに準備できます。また、複数の僧侶や法要の際の注意点、トラブル回避のポイントも押さえておくと安心です。心を込めてお布施を準備することで、葬儀を穏やかに、そして丁寧に進めることができます。初心者でも、「葬儀のこれから」などのサービスを活用すれば、費用や手続きに迷うことなく安心して対応可能です。